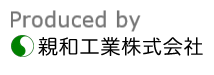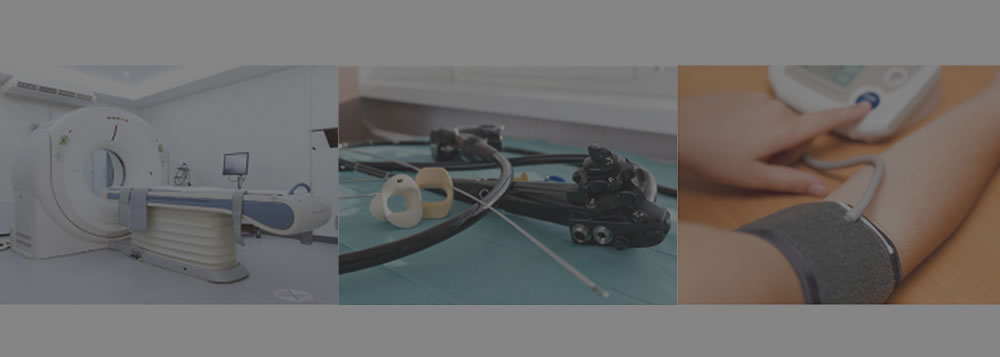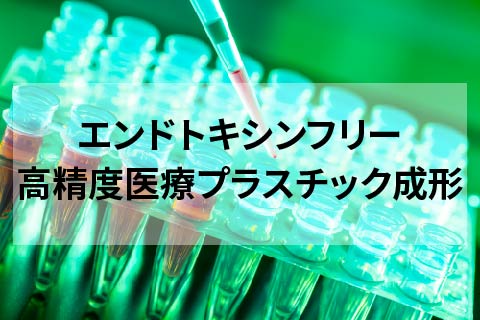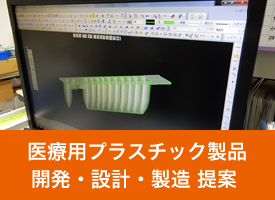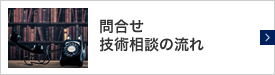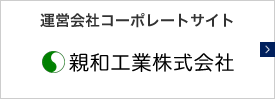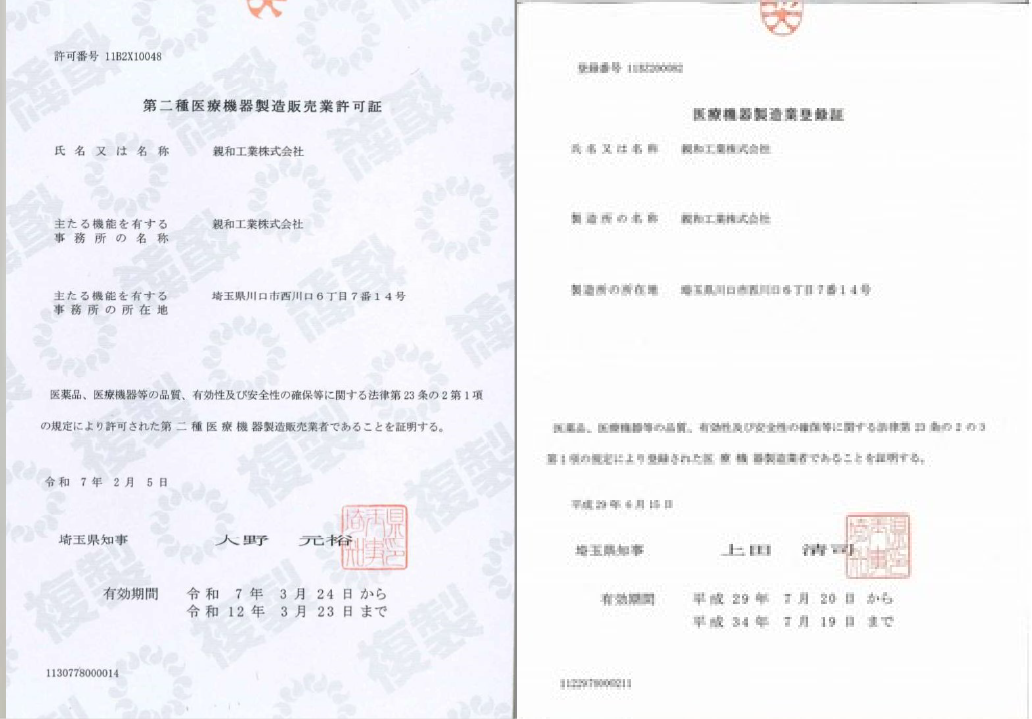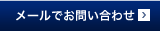エンドトキシンとは?
エンドトキシン(内毒素)とは、グラム陰性菌(例:大腸菌、赤痢菌、サルモネラ菌、レジオネラ菌など)の細胞壁に存在するリポ多糖(LPS:リポポリサッカライド)の生物活性成分であり、特にリピドAがその主な活性部分となります。エンドトキシンは、日本語では「内毒素」とも呼ばれます。エンドトキシンは、細菌が死滅・破壊された際に細胞壁から大量に放出されるほか、一部は細胞外小胞を介して増殖時にも微量が放出されることがあります。
エンドトキシンの語源
エンドトキシン(Endotoxin)は、ギリシャ語の「endo-(内部の)」と「toxikon(毒)」に由来する言葉とされています。19世紀末、細菌が持つ耐熱性の毒素が発見され、細菌が死滅した後に放出されることから「内毒素(Endotoxin)」と名付けられました。これに対し、生きた細菌が分泌する毒素は「外毒素(Exotoxin)」と呼ばれます。
グラム陰性菌とは?
グラム陰性菌とは、グラム染色法において赤みを帯びたピンク色に染まる細菌の総称です。細菌の分類方法の一つである「グラム染色」は、1884年にデンマークの細菌学者ハンス・クリスチャン・グラムによって開発されたもので、細菌の細胞壁の構造によって「グラム陽性菌」と「グラム陰性菌」に分類されます。
グラム陰性菌の細胞壁の特徴
グラム陰性菌の細胞壁は、以下のような構造を持ちます。
-
外膜(Outer Membrane):
-
グラム陰性菌特有の構造で、リポ多糖(LPS)を含んでいます。
-
LPSは外膜の外側に存在し、エンドトキシンとして強い免疫反応を引き起こします。
-
他にも、ポリン(Porin)と呼ばれるタンパク質があり、特定の分子の透過を制御します。
-
-
ペプチドグリカン層(Peptidoglycan Layer):
-
グラム陽性菌に比べて非常に薄い(2~3層程度)。
-
細胞の形状を保持する役割を果たしますが、グラム陽性菌ほど強固ではありません。
-
-
内膜(Inner Membrane):
-
細胞質を囲むリン脂質二重層。
-
重要な代謝機能や物質輸送を担っています。
-
この三重構造によって、グラム陰性菌は環境ストレスに対して強い耐性を持つ一方で、LPSがエンドトキシンとして働くため、感染症を引き起こしやすい特徴があります。
代表的なグラム陰性菌
以下は、ヒトの健康や環境に影響を与える主なグラム陰性菌の例です。
-
大腸菌(Escherichia coli):腸内に常在するが、一部の毒性株(O157など)は食中毒を引き起こす。
-
サルモネラ菌(Salmonella spp.):食中毒の原因となる細菌で、動物性食品に多く含まれる。
-
レジオネラ菌(Legionella pneumophila):温水環境に生息し、肺炎(レジオネラ症)の原因となる。
-
緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa):病院環境に多く、免疫力の低下した人に感染しやすい。
-
赤痢菌(Shigella spp.):腸管感染を引き起こし、激しい下痢を伴う細菌性赤痢を発症。
-
インフルエンザ菌(Haemophilus influenzae):小児の細菌性髄膜炎や呼吸器感染症の原因となる。
グラム陰性菌と抗生物質耐性
グラム陰性菌は、その構造上、多くの抗生物質に対する耐性を持ちやすい傾向があります。
-
外膜によるバリア機能:
-
β-ラクタム系抗生物質(ペニシリン、セフェム系)がペプチドグリカン層に到達しにくい。
-
-
薬剤排出ポンプ(Efflux Pump):
-
抗生物質を細胞外へ排出する機能を持つ菌株が多い。
-
-
耐性遺伝子の獲得:
-
プラスミドやトランスポゾンを介して、抗生物質耐性遺伝子を獲得しやすい。
-
これらの理由から、多剤耐性グラム陰性菌(MDRGN: Multi-Drug Resistant Gram-Negative Bacteria)が世界的に問題となっており、新しい抗生物質の開発や感染対策が急務となっています。
エンドトキシンの発生原因
エンドトキシンは、主に以下のような条件で発生します。
-
グラム陰性菌の増殖・分裂:エンドトキシンは、グラム陰性菌の死滅・破壊時に大量に放出される。一方、一部のエンドトキシンは細胞外小胞を介して増殖時にも微量が放出されることがあります。
-
細菌の死滅や破壊:抗生物質や殺菌処理によって大量に放出。
-
環境中のコンタミネーション:水、土壌、空気中に広く存在。
グラム陽性菌(例:ブドウ球菌や連鎖球菌)にはエンドトキシンは含まれず、代わりにエキソトキシン(外毒素)を産生することが多いです。エンドトキシンは環境中に広く存在し、水道水や食品、医療機器などへの混入が問題視されています。
エンドトキシンの特徴と生物活性
エンドトキシンは、ごく微量でも体に影響を与える物質です。体内に入ると、免疫細胞が異物と認識し、炎症を引き起こします。これによって発熱や血圧低下が起こることがあります。
エンドトキシンが少量であれば、免疫が適切に働き、体を守る作用があります。しかし、大量に体内へ入ると免疫系が過剰に反応し、重篤な症状(敗血症や多臓器不全など)を引き起こすことがあります。
またエンドトキシンは通常の消毒(アルコールや低温滅菌)では除去できず、250℃以上で30分以上の乾熱滅菌が必要です。特に、医療機器や薬剤では、エンドトキシンの管理が重要です。
エンドトキシンの主な特徴(表)
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 由来 | グラム陰性菌の細胞壁の成分 |
| 作用 | 発熱、血圧低下、炎症の原因になる |
| 耐熱性 | 非常に高く、通常の消毒では除去不可 |
| 影響 | 少量で免疫活性化、大量で敗血症のリスク |
| 不活化方法 | 250℃以上の乾熱処理が必要 |
エンドトキシンの構造
エンドトキシンは以下の3つの主要な構造要素から成り立っています。
-
O抗原多糖:細菌ごとに異なる構造を持ち、特異的な免疫反応を引き起こします。
-
コア多糖:O抗原とリピドAをつなぐ部分で、エンドトキシンの構造的安定性に関与します。
-
リピドA:生物活性の中心となる部分であり、宿主の免疫系を強く刺激する脂質部分です。リピドAはエンドトキシンの炎症誘発活性の本体であり、Toll-like receptor 4(TLR4)に結合することで、NF-κB経路を活性化し、炎症性サイトカインの産生を引き起こします。
パイロジェンとは?
「パイロジェン(Pyrogen)とは、発熱を引き起こす物質の総称で、エンドトキシンのほか、細菌由来のエキソトキシン、ウイルス由来のタンパク質やリポペプチドなどが含まれます。19世紀末に発見され、当初はエンドトキシンと同じ意味で使われていましたが、その後、ウイルスや他の微生物由来の発熱物質も含むことがわかり、より広い概念として使われるようになりました。
パイロジェンには以下のような種類があります。
-
エンドトキシン(内毒素):グラム陰性菌由来。
-
エキソトキシン(外毒素):グラム陽性菌由来。
-
ウイルス由来の発熱物質:特定のウイルスが原因となるもの。
エンドトキシンとパイロジェンの違いとは?
エンドトキシンはパイロジェンの一種ですが、パイロジェンには他の発熱物質も含まれます。以下の表でその違いを整理します。
| 項目 | エンドトキシン | パイロジェン |
| 定義 | グラム陰性菌の細胞壁成分 | 発熱を引き起こす物質の総称 |
| 由来 | グラム陰性菌 | ウイルス、細菌、代謝産物など |
| 耐熱性 | 非常に高い | 種類による |
| 影響 | 免疫活性化・敗血症 | 発熱、炎症反応 |
| 不活化方法 | 乾熱滅菌 250℃以上 | さまざま |
エンドトキシンフリーとは?
エンドトキシンフリーとは、医療や製薬の分野で、エンドトキシン濃度が規定値以下(例:注射用水では0.25 EU/mL以下)であることを示す概念です。医療機器や医薬品では、エンドトキシンの影響を避けるために、エンドトキシンフリーの状態が求められます。
エンドトキシンフリーを実現するためには、以下の対策が取られます。
-
高温乾熱処理:250℃以上で30分以上加熱。
-
特定のろ過フィルターの使用:エンドトキシンを除去できるフィルター(0.22µm限外ろ過膜など)。
-
クリーンルームでの製造:エンドトキシンの混入を防ぐ。
-
エンドトキシンフリー水での洗浄:製品表面からの除去。
-
専用検査装置での検査:エンドトキシンの残留を確認。
医療機器や注射剤は、エンドトキシンフリーの規格に適合していることが必要とされ、厳格な品質管理が行われています。
パイロジェンフリーとエンドトキシンフリーの違い
エンドトキシンとパイロジェン(発熱物質)は混同されることが多いですが、厳密には異なります。
パイロジェンフリーとは、発熱を引き起こす物質(パイロジェン)が検出限界以下であることを意味し、エンドトキシンに限らず、細菌由来のエキソトキシンやウイルス由来の発熱物質なども含みます。
一方、エンドトキシンフリーは、エンドトキシン(グラム陰性菌由来のLPS成分)のみが規定値以下であることを示します。
医療や製薬の現場では、「パイロジェンフリー」と「エンドトキシンフリー」が混同されることがありますが、エンドトキシンフリーであっても他の発熱物質が含まれている可能性があるため、必ずしもパイロジェンフリーとは限りません。
特に、エンドトキシンは耐熱性が高く、不活化が最も困難な発熱物質の一つであるため、エンドトキシンの管理が重要視されています。
そのため、一部の医療・製薬分野では、エンドトキシンを完全に管理できれば、実質的にパイロジェンフリーも達成できると考えられ、「エンドトキシンフリー」という表現が「パイロジェンフリー」と同義で使われることがあります。
エンドトキシンの滅菌方法
エンドトキシンはオートクレーブ(121℃、15分)や化学滅菌(アルコール、ホルムアルデヒド)では完全に失活しません。高い耐熱性を持つため、以下の特別な処理が必要です。」
-
乾熱滅菌(250℃、30分以上)
-
最も確実なエンドトキシンの不活化方法であり、金属やガラス製品に適用されます。
-
ただし、プラスチック製品には適用できません。
-
-
ガス滅菌(過酸化水素+オゾン)
-
最近の研究では、過酸化水素やオゾン処理によってエンドトキシンの生物活性を低下させることが可能であることが報告されています。ただし、完全な分解や除去には250℃以上の乾熱滅菌が必要です。
-
-
吸着・除去フィルター
-
エンドトキシンは水溶液中でミセル構造を形成するため、一般的なフィルター(0.22µmの限外ろ過膜)では完全に除去できません。エンドトキシン除去には、特殊な吸着フィルター(活性炭フィルターやエンドトキシンバインダー)が必要です。
-
透析液や注射用水の製造において、エンドトキシンの管理に重要な技術。
-
エンドトキシンは環境中のあらゆる場所に存在しているため、完全な除去は非常に困難です。そのため、医療機器や医薬品ではエンドトキシンの混入を防ぐ厳格な管理が必要とされています。
>>「DNA フリー」とは?生殖医療や遺伝子解析・細胞培養に必要な3つのフリーについて
>>遺伝子解析・遺伝子治療用プラスチック成形品の対応について
さらに詳細は、下記をご覧ください。
>>遺伝子解析・遺伝子治療・細胞培養・採血デバイス・不妊治療製品向け
エンドトキシンフリー高精度医療プラスチック成型品 開発・設計・製造